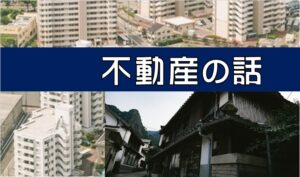『町内会―コミュニティからみる日本近代』
今回のブックレビューは「町内会」です。
町内会の副会長をさせていただいているおかげで、私にとって町内会は身近なものなのですが、町内の方にとってはどうでしょう?夏祭りや運動会には参加したいけど、町内会の日ごろの活動には参加したくないし、役員とかは受けたくないというのが、正直なところではないでしょうか。
私自身、町内会というものが一体どういった性質のものであるかしっかりと理解しないまま活動していたので、この本が出ていたとき気になっていました。とはいうものの、正直、軽い内容の本かなあと思っていました。しかし、実際に読んでみると非常にしっかりと研究されており、内容の濃さに驚きました。
昔から地域の集まりはありましたが、町内会の基本が出来上がったのは、明治時代だそうです。地方自治を進めていく中で、「旧村の実質的リーダーである豪農層は、政治的意思決定から遠ざけられ、既に決まったことを執行する行政への協力だけにその権限を限定されるという形」が形成されました。出来上がった明治地方自治制は「芸術品」とまで評されるそうです。その後、日本は第2次世界大戦に突入していきます。その流れの中、町内会は天皇制ファシズムを底辺から支える組織に変貌していきます。そのため、敗戦後、GHQは町内会を解体しました。しかしながら、現在町内会が存在するのは、行政が地方自治を円滑に進めるためには、日本では町内会の機能がどうしても必要だという理由からです。
現在でも、行政は、町内会に政治的意思決定機能を持たせることは行わず、行政への協力のみを求めています。(協力の報酬として、補助金等を支給しています。)
一方で、町内会を運営する人は高齢者が多く、年齢が若くなるにつれ町内会から離れていっています。町内会に行政の協力を行う体力はないのです。また、個人の意識も町内活動から離れていっています。地方創生・地域活性化を望むのであれば、今、町内会を含む地方自治のあり方を見直していった方がいいと思います。
なお、私事ですが、昨年一身上の都合で半年間町内会への参加活動を控えていましたが、今年の4月からまた町内会活動に参加させていただく予定です。(もう少し頑張ります!)
ちくま新書
『町内会 ―コミュニティからみる日本近代』
著者:玉野 和志
発行:筑摩書房 新書判 192ページ
定価 840円+税 書店発売日2024年6月7日
不動産に関する疑問質問などお気軽にお問い合わせください。
受付時間 9:00-18:00(水曜・第二火曜日定休) 電話番号 092-558-0157